
他店から学ぼう。「本屋B&B」で、店舗運営の“裏側”を覗いてきました。
先週、ついに正式オープンした透明書店。お陰様で連日大いに賑わっていますが、この連載では、もう少し準備の様子をお伝えしていきます。
今回は「他店に学ぼう!」ということで、人気独立系書店「本屋B&B」さんをみんなで訪ね、書店経営の裏側を覗いてきました。

以降はライターの中前結花さんに取材していただきました。

今日は場所を変えて、朝からとある書店の前で待ち合わせ。
東京世田谷区の下北沢と世田谷代田の間にある「本屋B&B」さん(以降、B&B)に来ています。
気になる新刊の他、個性的な棚の数々に約10,000冊の本が並び、店内では本(BOOK)と一緒にビール(BEER)まで楽しむことができるようになっています。
「これからの街の本屋」をコンセプトに掲げる同店が実際に運用されているのか….そのイロハを学ぼうと、今回みんなで足を運んだのでした。
これが、B&Bの朝。
「あ、遠井さん!」
「あ、おはようございます」

実は、透明書店の店長となる遠井さんは「研修」と銘打って、今年1月からここB&Bでお手伝いをさせてもらっています。
「開店のご準備ですか?」
「はい、開店前の掃除をしているところでした」
すでに数ヶ月間お世話になっていますから、開店準備は慣れた手つきです。
今日はB&Bの運営に携わっている、松村さんにお話をうかがいます。
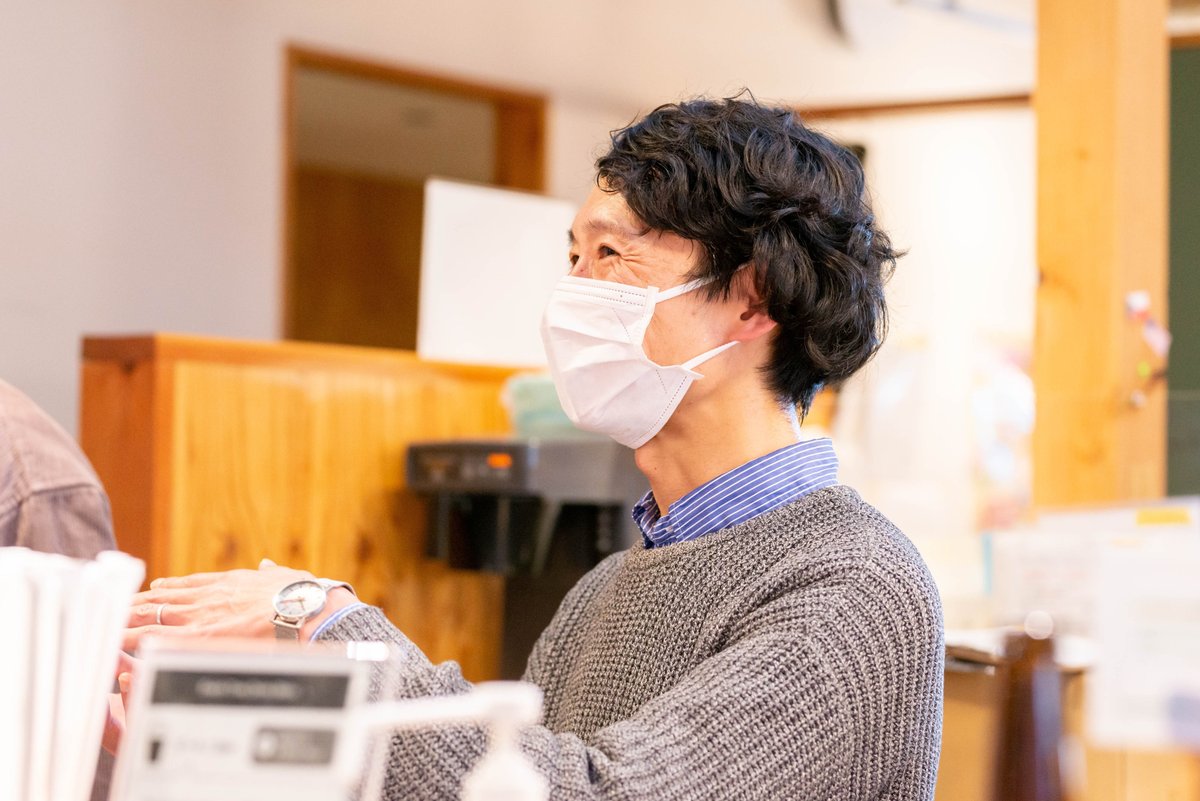
松村:
B&Bは、基本的には2人交代制で回しているんです。12時オープンなので、早い人は2時間ほど前にやってきて、掃除や届いた書籍の荷捌きをしていますね。
岩見:
朝出勤したら、この入荷書籍のダンボールが届いている状態なんですか?

松村:
そうなんですよ。取次さん(出版取次:出版社と書店の間をつなぐ流通業者)には鍵を渡しているので、こうして毎朝店内まで運んでくれているんです。雑誌とその日の新刊、それから新しく取り寄せた書籍なんかが、まとめてドンと置かれています。
岡田:
ダンボールの中身はすべて開店前に、棚に収めるんですか?
松村:
本来はそうしたいところですが、入荷量によっては難しいこともあるので、絶対に終わらせておくのは、ダンボールの荷捌きまでですね。開店してから棚に収めることが多いです。
あと済ませておくのは、掃除やお釣りの準備ですね。B&Bでは、現金の取り扱いは、もう半分以下になっちゃいましたけど。

岡田:
現金を扱わず、クレカやQRコード決済だけだと厳しいでしょうか?
松村:
なるほど、そうしたいんですね。それぐらい攻めたお店も増えてきていますが、B&Bのような書店の場合は、まだ現金払いをご希望の方が半分程度いらっしゃるので、今は少し厳しいかもしれませんね。お店の近くの銀行の口座を開いておくと、おつりの用意などに便利なので、おすすめします。
岩見:
たしかに……。今はネット銀行しか口座を用意していないのですが、そういう観点もあるんですね。
岡田:
防犯上の観点とか、両替手数料が上がってるとかも聞きますし、ぼくは完全キャッシュレスを諦めたくないところですね……。検討します。
FAXは必要?本屋業は紙の文化

岡田:
「返品」のダンボールも業務中に作るということですよね?
松村:
そうですね。返品する予定の書籍をまとめておく「返品棚」をバックヤードに作ってるんですよ。ひとまずはそこに置いておいて、溜まったらダンボールにまとめるといった形です。
松村:雑誌は返品期限がありますし、返品予定の本も、痛みや汚れがないか確認する必要があるので、注意が必要です。出版流通における委託・買切のルールにはグラデーションがあって、一概には言えないのですが、たとえば、返品のときに、出版社さんの了解書が必要なケースもあります。その場合の返品了解のやりとりは、まだFAXが主流ですね。
「返品」とは?:新刊書籍は出版社が決定した定価でしか販売できません。これを「再販制度」といいます。
そして仕入れた本については、一定の条件で返品できる商品もあります。出版業界ではこれを「委託」と呼ぶため、出版業界独自の特徴として「再販・委託制度」とまとめて呼ばれたりします。

岡田:
FAXって、やっぱり是が非でも必要でしょうか……。
松村:
そうですね。本屋業界は、FAX文化がまだ根強いと思います。いま言ったような返品作業だけでなく、新刊情報の入手や発注にもFAXを多用するんですよ。
岡田:
なるほど……。その「紙の文化」を少しでも楽に便利にできるような仕組みを考えて作ることができたら、すごくいいですよね。
松村:
そうですね。実際に大きく変えることができれば、便利になりそうですし、とてもおもしろいですよね。

棚に何を並べるか

岩見:
それぞれの棚と、揃えている書籍についても教えてもらえませんか?
松村:
はい、もちろんです。
まず、入口の正面に当たる場所には新刊・近刊を並べていて、もう一つの入口の正面には、文学寄りの新刊を並べるようにしています。
そのほかは、ジャンルごとに棚を作っていて、文学やアート、デザイン、ビジネス、人文科学、社会科学、自然科学、ジェンダー、フェミニズム……。海外文学を多く取り揃えているのも特徴だと思います。
そう言って、松村さんはそれぞれの棚を案内してくださいました。

岩見:
店内には、POPをまったく設置していませんよね。
松村:
そうですね、最近は少しずつ試したりもしていますが、基本的にはほぼ付けていません。B&Bの場合は、偶然の出会いを求めて来てくれる人が多いので、お客さん自身が気になった本に手を伸ばしやすい環境を意識しています。
岡田:
やっぱり冊数や棚はどんどん増えていきましたか?
松村:
はい、これは本屋あるあるかもしれません(笑)。どうしても「良い本を少しでも多く並べたい、見せたい、知ってほしい」となってしまうので。今は、オンラインショップでも本を取り扱ってますしね。

岡田:
透明書店も、オンラインショップは開設したいと考えているんです。
松村:
それはぜひやっていただきたいですね。お店の世界観も表現することができますし、「どうせ買うのなら、応援しているあのお店で買いたい!」とお店自体のファンの方や、遠方のお客さんが買ってくださることもあって、それはお店としても嬉しいです。
今は、気軽に始められるECサイトサービスも増えていますし、B&Bのような小さな本屋でも気軽にスピード感をもってチャレンジができますよね。
岡田:
「小さいからこそスピーディー」というのは、スモールビジネスのおもしろいところですよね。
松村:
そうなんです。「文学フリマ」などのイベントに出かけては、常に新しいもの、面白いものを探して仕入れています。
岡田:
たしかにおもしろい書籍の開拓にも力を入れないといけないですよね。それについても、なにかテクノロジーを使ったいい方法がないか考えたくなってきました。

「本と雑貨」の贈り物

岩見:
書籍だけじゃなく雑貨も並んでいますが、たくさん手に取っていただけるものでしょうか?
松村:
そうですね。うちでは雑貨も含めたフェアを行うこともあって、作り手さんから商品をお預かりさせて頂いて、在庫を持たずに販売していることが多いです。
雑貨とそれに絡めた書籍を並べることで、同時に買っていただけることもありますし、何よりプレゼントとして購入いただけることが多いようです。本と合わせてギフトにしたい、とラッピングを要望される方も多いですよ。


岩見:
そうなんですね。ラッピング……ちっとも考えられていませんでしたが、必要そうですね。
ギフトにもぴったりなものをポップアップのように展開すれば、蔵前という土地柄もあって、選んでいただけるかもしれません。
松村:
うんうん、いいですね。
岡田:
書籍と雑貨をセットで贈るっておしゃれですよね。そういう風習を作っていくのも、おもしろそうです。
連続性のあるイベントを

松村:
あとは、B&Bではほぼ毎日、19時半頃からイベントも開催しているので、その準備や運用、後片付けも仕事に入ってきます。
岩見:
「ほぼ毎日」というのがすごいですよね。
松村:
著者の出版記念トークイベントが多いですが、全〇〇回の講座みたいなものも開かれています。
岡田:
そういうのもいいですよね。単発のイベントももちろんやりたいんですが、連続性を持った取り組みをしたり、イベントの集積で何かを作ったりできるとおもしろそうだなと思っているんです。
松村:
それはいいですねB&Bの運営元の「numabooks」では出版事業もやっているんですが、これまでのB&Bの経営を活かした本づくりなども行なっていて、それをまたB&Bで販売したりしているんですよ。

岡田:
まさに、そういうことができるといいなと思っていて。「自分たちで本を作る」というのも、また売上の助けになるビジネスなのかなと。
グッズもイベントも別々の事業だと思ってましたが、一緒に考えていくのがいいんでしょうね。本というものを起点に、地域と繋がっていくような体験を考えていかれているところも、参考にしたいなと思いました。
出たな!スリップ作業
そして……。松村さんとのお話の最中、岡田さんや岩見さんはあることがずっと気になっていました。
「遠井さんは、ずっと何をされているんですか……?」
「スリップを作ってるんです……」
スリップ——。この作業については、実は連載第1回目でも話題にのぼっていたんです。


岡田:
高価な専用レジを導入できない小さな店舗だと、本に挟まっているあの紙(スリップ)を抜いて、あとから集計することで、何が売れたか把握することも多いみたいです。ただ、最近は大手書店ではほぼ専用のレジをつかっていたり、出版社のコスト削減の流れでスリップも減っているらしくて。

そう、遠井さんはスリップの入っていない本のために、プリンターと裁断機で、スリップを手作りしていたんです。
岡田:
もう、2時間ぐらいスリップ作りに割かれてますよね……。
遠井:
そうなんです……。特に今日は入荷が多い日だったので。それにしても大変です。
岩見:
会計のときにも忘れずに抜かなきゃいけないですけど、自分がレジ担当だったら、忘れてしまいそうで怖いな。何が売れたかわからなくなるので注意が必要ですね。
岡田:
スリップには賛否両論あるみたいですが、透明書店としてはデジタルで対応していきたい気持ちがあるので、この作業時間はなるべく無くせるといいなと思っています。代わりに、いい本を掘り出す時間に充てられるといいなと感じました。
課題があるからワクワクする

—— 3時間いろいろと見て、教えていただいて、いかがだったでしょうか?
—— スリップは、どうしますかね……。
岩見:
めちゃくちゃ勉強になりましたね。特に雑貨の取り扱いやプレゼント需要のお話がとても参考になって、透明書店でもぜひ取り入れたいなと思いました。
それから返品についても。想像以上に繊細なやり取りをされている印象だったので、気をつけないといけませんね。
あとは店内をよく見てみたら、B&Bの店内にはエアコンがいっぱいあったんですよ。透明書店は、現状1個の予定なんだけど、大丈夫なんだろうか、とか。細かいところがたくさん気になったので、少しでも取り入れられるものは取り入れたいなと思いましたね。

岡田:
スリップ、本当に大変そうでしたね。印字してるってことは、もともとどこかにはデータがあるってこと。データを一旦紙(スリップ)にして、またデータ化している……。
僕たちfreeeのプロダクトも「みんな、レシートや請求書を転記してる」「つまり、データを紙にしたものを、またデータ化してる」「それって無駄じゃないか」っていうのがはじまりだったんですよ。
それで、銀行とかクレジットカードと情報を同期してデータをとるようにしたんです。それと同じことだなあと当時を思い出して、なんとかして「スリップ作業」を無くしたいなと思いました。
——その決意、となりで拝見していて「静かに燃えてらっしゃる……」とヒシヒシ感じておりました……(笑)。参考にしたいこと、課題に感じること、いろんなものが事前に見られて、とってもありがたかったですね。
岩見:
本当にそうですね、たくさん教えていただいて感謝ばかりです。
グッズとイベントとお店の関係性もすごく考えられていて、透明書店もあんなふうに愛される店にできればいいなと思いました。
岡田
快晴だったこともあって、お客さんたちがランチを外で食べている様子も印象的でした。他のお店の続きで本屋があって、お昼を食べながら本を読んだりしてほしいなと。蔵前でも、周りの飲食店やいろんなお店を含めた体験づくりを考えられるとおもしろそうですよね。本当に参考になりました!

——蔵前の街を一層盛り上げられるような取り組みができると素敵ですよね。本屋B&Bさん、今回はどうもありがとうございました!
次の記事では、AIの副店長!?をご紹介しています。ChatGPTは、本屋とどう融合していくのか…
◆中前結花
ライター・エッセイスト。下北沢の書店巡りを日課にしている。著書にエッセイ集『好きよ、トウモロコシ。』(hayaoki books)など。
撮影:飯本貴子 デザイン:Samon inc. 編集:株式会社ツドイ
お知らせ:note無料メンバーシップ「透明書店バックヤード」
透明書店をもっと身近に感じてもらくて、書店経営の裏話を語る無料のメンバーシップ『透明書店バックヤード』を開設いたしました!「参加する」ボタンを押すだけで、無料で気軽にメンバーになることができます。

記事では盛り込みきれなかった、書店経営の裏側を不定期Podcastでお届けします。
まるでバックヤード(従業員控え室)でくりひろげられるような愉快な内緒ばなしを、ぜひお楽しみください。

