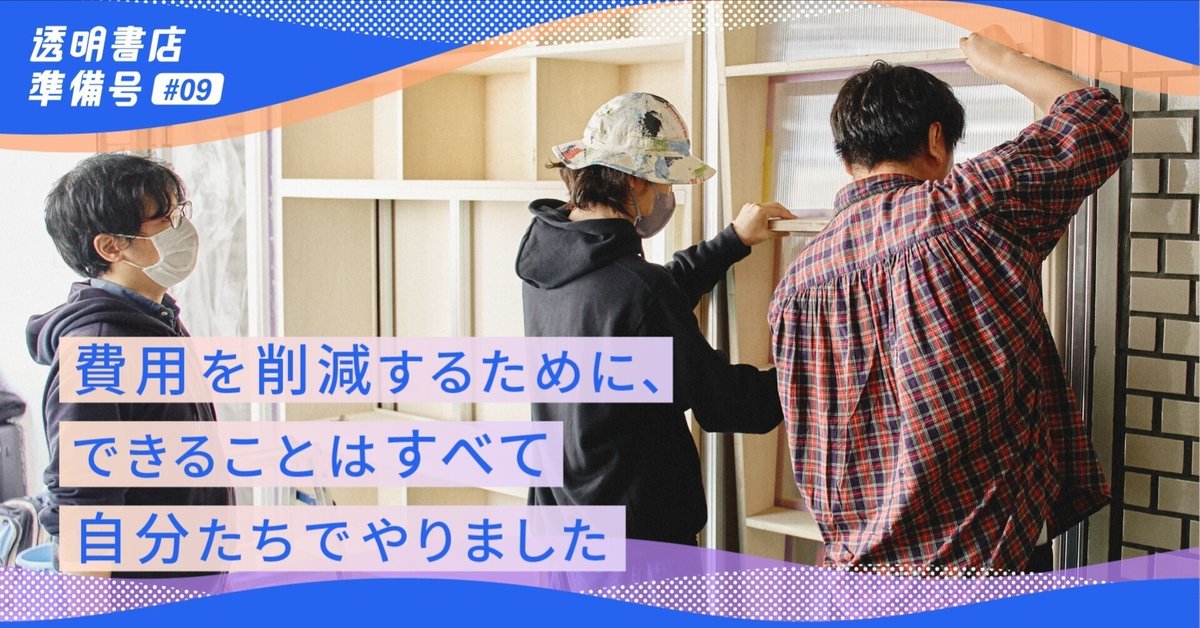
限られた予算を削りながら、内装で「透明」を表現するには?
4月にオープンした透明書店。オープン以来、お陰様で連日大いに賑わっていますが、この連載では、もう少し準備の様子をお伝えしていきます。
今回は「透明」をコンセプトに作り込んだ内装について、建築家の「建築みるぞー」さんにも加わっていただき、たっぷりとお話しします。
以降は、オープン直前の内装工事中に、ライターの中前結花さんに取材していただいたものです。

久しぶりに、蔵前のオープン予定地にやって来ました。
取材として訪れるのは2度目。ただ、この数ヶ月どうにも気になってしまって、近くを通るたび「どうなっているだろう……」と覗いてしまう場所でもありました。
ところが——。
「ここまで進みましたよ」
「……ええ! これはすごい」

この2週間で、内装工事は予想以上に進んでいました。緑色だった床はグレーに染められ、壁にはすでに本棚がいくつも並べられています。
また天井で剥き出しになっていた配管は、クリーム色からシルバーに塗り替えられ、キラリと輝いているのでした。
透明書店の内装は、「できることは自分たちで」というスタイル。床も配管も塗装したのは、freeeの社員のみなさんです。そして今日は、棚の塗装を進めるため、岩見さん、岡田さん、店長の遠井さん、freeeの有志メンバーの方々がいらしています。
現場を取り仕切っているのは、建築設計を手がけた「建築みるぞー」さんです。
「はじめまして」
「はじめまして、今日はよろしくお願いします」

自分たちの手で塗ること
——すっかり書店らしい雰囲気になってきましたね。みなさんが棚に塗られているのは、コーティング剤か何かですか?
建築みるぞー:
今塗っているのは、オイルステインという塗料なんです。この棚はシナ合板という素材でできているんですけど、白く塗りつぶしてしまうのではなくて、この半透明のオイルステインを塗ることで“木目が透ける”ように仕上げるんです。
塗装ひとつとっても、「透明」「透明感」を意識した技術や材料を選んでいますね。

——すごい。細部までコンセプトが行き届いているのを感じます。
岩見:
なかなか奥深い「透明」の表現ですよね。
塗る作業も思いの外、楽しくて。先週は、みんなで床を塗ったり、顔や服にペンキをいっぱい浴びながら壁を塗ったりしたんですけど、手伝ってくれているメンバーも楽しそうにやってくれているので助かっています。
——そうか、壁もみなさんで塗装されたんですね。「自分たちの手で作り上げた」という実感も湧きそうですし、スモールビジネスのスタートとしてすごく良い工程ですね。
建築みるぞー:
そうですね。もともとは職人さんに依頼した場合に発生する費用を抑えるために、「できるところは自分たちで」という手段を取ってもらうことにしたんですけど、そうすることで、お店が出来上がるまでの工程にも透明性を持たせるようなことができました。
それに、freeeに勤める方々がスモールビジネスを理解するために運営する透明書店なので、多くの方に関わってもらうことは価値ですもんね。ですから、この方法を選んで、今はとてもよかったと思っています。

濃密な「透明」ディスカッション
——お話をうかがっていると、みるぞーさんは、岩見さんや岡田さんとかなり深くディスカッションされて、考えを共有されているように感じます。
建築みるぞー:
もともと岩見さんとは面識があって、このお店のお話をいただいたのは昨年の10月のことでした。そのときにfreeeの経営理念の説明から始まって、何十枚もパワーポイントの資料を見せてもらったんです。これは大変だと思いました(笑)。
だけど、それを読み込んだあと、こちらからもヒアリングをさせてもらうことで、どんどん理解が深まりましたね。論理的に「こういう事例が近いかもしれない」といった話をしたり、直感的に「それって、こうするとおもしろいんじゃないか?」なんて話をしたり。
少しずつ具体的な内容に掘り下げながらディスカッションして、ラフスケッチをいくつも見せながら進めていきました。

——相当、時間をかけられましたか?
建築みるぞー:
丁寧にやりながらも、スピード感は持てていたと思いますね。1ヶ月半程度で大体の設計の内容は決まったんですよ。そこからは、設計したものを工務店さんや家具屋さんに見てもらって見積もりを出して。
「どこを諦めるべきか」「どこを削るか」という部分で提案・相談させてもらって着地させていった、という感じです。

——最初に、ぎゅっと濃密なお話し合いができていたんでしょうね。
建築みるぞー:
そうですね。早い段階で「透明書店の透明性は、単純にガラスで作るような透明じゃない」「奥深さや、変化を知れること、が大事なんじゃないか」という話を一緒にできたのが良かったんだと思います。
制限があるなかでも、結果的にその理想にはかなり近づけたように感じています。
「インビジブル」と「スケルトン」
——「単純にガラスで作るような透明じゃない」というお話が出てきました。たしかに、「透明」というコンセプトにしては、透明な素材のものが少ないですよね。みるぞーさんが考えられた「奥深さ」や「知れること」というのは、どういうものなのでしょうか?
建築みるぞー:
透明な棚に透明なカウンター、といった見せ方もあったと思うんですけど、見た目の透明性にフォーカスして作ってしまうと、どうしてもキャッチーなところで終わってしまう気がしたんです。もう少し持続性のある、みんなの思い入れが深くなるような透明性を考えたいと思いました。
たとえば、この床はあえて全部を塗りつぶさず、店の奥側はそのまま残しているんです。こうしたのは、かつての床も一部見せることで、時間の流れや歴史に透明性を持たせたかったからなんですよね。


——……それは、育ってきたプロセスを見せる「透明性」ということですか?
建築みるぞー:
そういうことです。この背平置き用の本棚に透け感のある素材を使っているのも、見た目の透明さという意味合いよりは、棚を置くことで見えなくなってしまう古い壁が、少しでも見えている方が時間の重なりが可視化されておもしろいなという考え方です。
——ああ、この素材であれば、今回の改装で隠れてしまう古いドアもちらりと見えますね。
建築みるぞー:
はい。他にも軽量鉄骨下地(LGS)を、本棚のデザインの一部としてあえてそのまま剥き出しにすることで、あとで自分たちでもカスタマイズしやすいように内側の構造体を見せる「透明性」を採用している箇所があります。
少し専門的な話になりますが、透明性には「インビジブル」と「スケルトン」がある、という話をしていました。
簡単に言うと、「インビジブル」は物質的な透明。ガラスだとか透明プラスチックで表現できるものですね。一方で「スケルトン」というのは、 すぐには読み解けないけど、奥行きやレイヤーを感じることのできる概念的な透明性なんです。
たとえば日本の十二単とかって、物質的には不透明ですけど、12枚が重なっていることを理解できるじゃないですか。

——……見た人が構造を理解できる、想像できる、というのが「スケルトン」ということであっているでしょうか?
建築みるぞー:
ええ、簡単にはそういう理解でいいと思います。
この「透明書店」は、経営や作り方もオープンに、透明にしていくものですし、どういう仕組みで内装が成り立っているか、どういう時間の経過のなかで今があるか、そういったものが浮かび上がってくるような「スケルトン」の方が大事なんじゃないかと考えたんです。

——はあ、なるほど。表面的でなく、深い部分で「透明」を味わうことができることを大切にされた。
建築みるぞー:
そうですね。ただ、それだけだともちろんお客さんにコンセプトを理解してもらうのは難しいですから、実際には「インビジブル」も部分的に織り交ぜながら設計していたりします。
——だから、入口の扉などシンボリックな部分にはガラス素材もしっかりと活かされているんですね。
建築みるぞー:
まさにその通りです。そのバランス感は、今回とても大切にしました。表面的な意味での「インビジブル」な透明にも気を配りつつも、体験としての奥行き感を生み出す「スケルトン」を大事にすることで、一見しただけでは分からない透明書店ならではの「透明」をデザインすることを心がけましたね。
予算内でどう実現するか
——事業計画の資料を見ると、内装の予算は300万円です。これだけの家具を作ったり、天井を抜いたり、壁を抜いたりするのは大変だったのではないでしょうか?
岩見:
最初から厳しい戦いになることは覚悟してはいたんですけど、初期の見積もりでは予算を大幅にオーバーしていて焦りました(笑)。
ただ、その時点でみるぞーさんが「ここは減らせると思う」みたいな赤入れを、見積もりにたくさん入れてくれてたんですよ。そのおかげもあって、「じゃあこうしよう」「ここは諦めよう」という議論がすごくスムーズにできました。たとえば、最初は開閉式の二段構えの本棚を作りたいと思ってたんですけど、オープン時は諦めよう、という判断をしたり。

建築みるぞー:
どうしてもやりたいことを詰め込んでいくと、金額は驚くほど高くなってしまうんですよね。
ただ、最初から「最小限」を意識して「何をやりたかったんだっけ?」というような中途半端な完成を目指すよりも、まずはやりたいことを全部並べて詰め込んで、そこから削っていくことをおすすめしています。そうしなければ方針も見出せないと思うので。
——なるほど。まずは「理想系を考える」ということも重要なステップなんですね。
岩見:
これが、見積もりの調整前と調整後の差分です。緑色で着色した部分は、自分たちの手を動かすことで、費用を抑えた部分です。

岡田:
「建具・家具・造作」の項目が大きく減っているのは、先ほど話していた二段構えの本棚をカットしたり棚数を減らした影響です。木材の価格がやっぱりすごく高騰しているので、その影響もあって、想像よりもかなり高い金額になっていましたね。
——いちばん大胆な「削減」は、どこでしたか?
岩見:
やっぱり奥の部屋の完成を、一旦すべて諦めたところじゃないですかね(笑)。

——この部屋の進捗だけが気になっていましたが、ここは一旦このままにしておく、ということでしょうか……?
岡田:
そうなんです。もともとは、この部屋も天井を抜いて照明をつけて、本棚を設置しようとしてたんですよ。だけど、どうしてもコスト的に足が出てしまうので、優先順位を下げることにしました。
ただ「何もしない」というのは家賃がもったいないんで、ここはしばらく「不透明な部屋」と名付けて、用途を募集しようと思っています(笑)。
——お客さんから募集! それはおもしろいですね。
岡田:
コラボや展示のご相談をいただいてもいいですし、たとえば「会議室として貸してください」というご相談があってもおもしろいかなって。
まさに「行き先不透明」ですが、未定だからこそできるおもしろいことがあるはずなので、この部屋を使って、いろいろ実験したいと考えているんですよ。(※現在も募集中です。詳しくはこちら )

常に変化のある店作りを
——選書などソフト面も非常にこだわって作ってこられましたが、ハード面である内装も、岡田さんと岩見さんの考える理想のものになりそうでしょうか?
岩見:
そうですね。「透明」というコンセプトを軸に、この予算感で仕上げたとは思えないほど、かなり深いところまで考えて設計していただいているので。すごくおもしろいものになりそうです。
最後にガラスの扉と、いちばん奥の壁にくらげのロゴを貼り付ける予定なんですけど、そうすると一気にお店っぽくなるでしょうね。お客さんにどう受け取っていただけるのか、今からめちゃくちゃ楽しみです。
岡田:
この内装のおかげで、「透明」の捉え方や考え方がさらに深まりました。
建築みるぞー:
ちなみに、入口に近い店の手前部分は、本がきれいにディスプレイされているんですけど、奥にいけばいくほど、棚はストレージ的な扱いになっていって、まだ棚に並べる前の仕入れた状態の本が並んでいるんです。
つまり、本屋さんの運用のプロセスまで透明になっているというイメージなんですよ。
入り込んでいくほど、広がりや奥深さを感じることができるようなお店にしたいと思っていたので、そこも含めて理想的なものが出来上がりそうだと思っています。

——すごい。来るたびに、発見が増えるような場所になりそうですね。
建築みるぞー:
実は、岡田さんと岩見さんもそこは非常に大事に考えられていて。本棚の一部も可動式にしています。場所や向きを変えられることで、内装やレイアウトに変化を持たせられたらと考えました。

——なるほど。二段構えをあきらめたとのことでしたが、可動式をあきらめずに実現されたのは、そういうお気持ちからだったんですね。次来るときには、棚の配置も変わっているかもしれないですね。
岩見:
そうなんです。くらげモニターや本の入荷だけでなく、内装でも何度も訪れたくなるようなお店づくりをしていければと思います。「いつ来ても新鮮でおもしろい」というのが、いちばんかっこいいと思うので。
——経年の変化も楽しめそうな作りですし、オープン後も愛着を持ってずっと育てていけそうですね。まずは完成を楽しみにしています!

今回で「準備号」は最終回。次回は特別編として、いくつも事件が巻き起こった透明書店オープン時の様子をお届けします。お楽しみに。
次回特別編はこちら
◆中前結花:ライター・エッセイスト。下北沢の書店巡りを日課にしている。著書にエッセイ集『好きよ、トウモロコシ。』(hayaoki books)など。撮影:芝山健太 デザイン:Samon inc. 編集:株式会社ツドイ
お知らせ:note無料メンバーシップ「透明書店バックヤード」
透明書店をもっと身近に感じてもらくて、書店経営の裏話を語る無料のメンバーシップ『透明書店バックヤード』を開設いたしました!「参加する」ボタンを押すだけで、無料で気軽にメンバーになることができます。

記事では盛り込みきれなかった、書店経営の裏側を不定期Podcastでお届けします。
まるでバックヤード(従業員控え室)でくりひろげられるような愉快な内緒ばなしを、ぜひお楽しみください。

